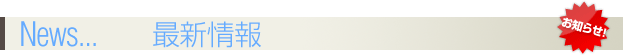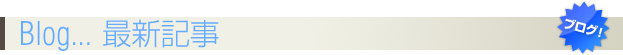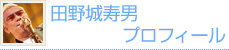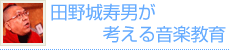アートって何?
「十勝毎日新聞」1997年10月31日〜11月11日 インタビュアー:後藤一也
「1991年モントルージャズフェスティバルに出場しながら、日本の音楽業界に違和感を感じ、昨年2月、帯広に移住したサックス奏者・田野城寿男(39)。
移住の理由は「ビジネスではなくアートをやりたいから」。ひとりのアーティストの創作風景や芸術観を紹介しながら、アートの影にある人生観に迫りたい。
レッテルで収めきれない・・・

1997年7月12日土曜日。東京・原宿は雨が降っていた。ラフォーレ周辺はさすがに個性豊かな若者たちでにぎわう。
このファッションビルで荒木経惟写真展「A人生」は開かれていた。会場内には今年2月に帯広でこの写真展が開かれたときと同じように、田野城寿男のオリジナル曲が流れている。その音楽を写真との競演として楽しもうという試みで、その夜、田野城とアメリカ人ピアニスト、ジョナサン・カッツのライブが行われた。
2週間前の写真展初日。荒木は初めて会った田野城に「問題がなければライブの様子を撮影して写真とのコラボレーションの形でビデオにしたい」と突然言い出した。「荒木さんは出会ったときに『あ、何か感じるな』って思ったって言うの。人と人とは出会い一発だからって」と田野城はそのときの様子を語る。
会場にはビデオの撮影機材が並んでいた。荒木が会場に姿を現したのは開演の30分前だった。演奏はジャズとも現代音楽とも言えない叙情的で美しい音楽だった。写真に取り囲まれ、それを写した写真家本人を前にした演奏は、緊迫感にあふれるものだった。
会場を後にするとき、田野城はふいにこう語った。「まさか東京でこういう音楽ができるとは思わなかった。ジャズやロックというレッテルで収めきれない音楽を取り仕切るプロデューサーは日本にはいない。そういう感性を理解して広い視野で音楽を見ているプロデューサーはいないの。でも僕自身はこうしたスタイルの音楽が1番ナチュラルになれる。」
ラフォーレを出ると、雨はまだ降り続けていた。若者たちであふれかえる週末の夜の雑踏の中を、田野城は大きな体にサックスを担いで足早に歩き出した。
どれだけ自分になるかということでしょう
生き方・・・素の自分になること

写真家・荒木経惟が田野城に「コラボレーションビデオを作ろう」と突然言い出したのは、なぜなのだろうか。「あ、何か感じるなと思った人間」と会ったときはセッションをやってみたいのだと、荒木は言ったという。
田野城が荒木の申し出を受け入れたのは、荒木に自分と同じ「ベクトル」を感じたからだ。「荒木さんの方が年も上だし経験も多いから自分と等しいという気はないが、どこに向かおうとしているかという方向性は共感できた」(田野城)。
「ベクトル」という言葉を田野城はよく使う。彼にとって「ベクトル」とは、“自分の生き方の方向性”という意味だ。「ステータスより素の自分になることを求めること。そこに荒木さんと同じベクトルを感じた。
本当の自分が何なのかということはまだまだこれからのテーマなんだけど、自分の羅針盤がどこを向いているかは、はっきりと分かってる。それをカモフラージュして、うそをついて、多少ズラすことも、やろうと思えばできるんだけど・・・」
だが、自分の方向性や個性を多少とも殺して、周囲に合わせてしまってはそれはアートとは言えないと、田野城は感じている。
当の荒木のほうは『週間朝日別冊・現代ニッポンにおける人生相談』のインタビュー記事の中で、こう語っていた。
「自分が違う風になろうとかなんとかじゃなくて、自分になっていく。どれだけ自分になるかということでしょう。(中略)人生は深く考えちゃいけない。深く考えることは疲れるし、暗くなるだけでしょ」(笑)
そばに愛・・・永遠のテーマ
「荒木さんは、奥さんが亡くなった後、芸術家として弱くなったんじゃないかな。陽子さんは荒木さんにとって本当の彼のプロデューサーだったと思うよ」。東京・原宿で開かれた『A人生』写真展を観(み)て、田野城は荒木について感想を漏らした。
『A人生』はガンで亡くなった荒木の愛妻・陽子との結婚から死別までを私小説風にまとめた写真展だ。芸術家にとって大切なのは“良いパートナー”が見つかることなのだと、田野城は言う。
「パートナーがモノを創(つく)っていく場合、とても重要になってくると思う。僕がどういう人間かということを客観的にも主観的にも理解してくれる人がそばにいると、自分が伸びていく。モノを創っていこうという勇気が生まれてくる」
この田野城への取材の後、今年9月に出版された荒木経惟の自伝『天才になる!』(講談社現代新書)の中で、荒木はこう述べている。
「天才は誰(だれ)でも持ってるんだよ。天から才能はもらってるんだ。それを自分だけじゃひっぱり出せないから、誰かが引っ張りだしてくれる」
芸術家がそれまでの美の流れとは違う独自の世界観を打ち出すこと−、田野城流に言うと自分の「ベクトル」を行くことは、そこに芸術的な価値があるにしろ無いにしろ、とても勇気のいることに違いない。
「自分が本当に思っていることを言い続けることはマイノリティーになるし、孤独なこと。アートは一人ではつくれない。自分のベクトルを最大限発揮できる力を与えてくれるパートナーが大切だと思う」
創作活動自体が人生だから、作品の中には愛と死しかない
美しく刹那的な感覚〜死を意識し、曲に反映

『Gaudi』をはじめとする田野城のオリジナル曲の特徴は、美しく刹那(せつな)的な感覚だろう。
「人生は愛と死だと思う。創作活動自体が人生だから、作品の中には愛と死しかない」と田野城は言う。その人生観と作品はどう結びつくのだろうか。「人間は間違いなく死ぬということは分かっているんだけど、(日本では)どこか“死”というものがパステル色にかけられて、分からなくさせられているような・・・」
そこまで言うと、田野城はふと気付いたようにこう切り出した。
「ニューヨークは殺人やギャングが多かったりするでしょ。なぜ、僕がニューヨークを好きなのかと言えば、毎日家に帰ると『きょうも生きていて、うれしい』という生活をさせてくれるから。死を身近に見ることによって、頑張って生きていこうという気になる。日ごろからそう感じられる生活をしないと、人に対しても素直になれないんじゃないかと思う」
人間はいつ死ぬか分からないということを意識することで「死からインスパイヤされるものがある」という。「日本では死の場面というものをなかなか見ることができないから、分からなくなっているのかもしれない」限りある一度だけの人生だからこそ、頑張って生きること−。ただ、美しく聞こえるメロディーの中には、彼のそんな精神的なメッセージが反映されている。
人間はいつか死ぬんだ
生と死について田野城が意識し始めたのは子供のころからだったという。出身は原爆の街・広島。「人間はいつか死ぬんだということを街ぐるみで教えてくれた」と笑う。広島市内の学校の校庭の下には原爆の犠牲者たちが埋められているのだという。校庭の下は骨だらけになのだと、小さいころから聞かされていた。
「小学生のとき、原爆ドームの周辺を歩いて妙に“死”というものを考えた。それで学校に行かなくなった」 毎日学校に行かずに、広島川の原爆ドームのほとりで魚釣りをして過ごした。河口に近いその辺りは、海魚と川魚が交じり合い、潮の干満に合わせて川も満ちたり引いたりする。地球が生きているということや、自然と人間との調和ということを、その潮の干満から教わったのだという。
「学校で教える常識や真理と、自然の動きがちぐはぐに見えた。自然の摂理ということについての考えが学校の教室の中にはまるっきり無くて、取って付けたような別のものが学校という空間の中で動いているという感じが、どうも我慢できなかった」
以来、高校卒業まで田野城はずっと学校嫌いだった。逆に、学校へ行かず、四季折々の変化を見せる自然の中に自分をひたしているほうが生きているという実感があった。「結局、小学生のときから自分にとっての哲学があったわけだ」と田野城は笑った。
音楽はスピリチュアルで、エモーショナルなものだ
目指す方向ジャズ・・・

高校に進学してからも田野城の学校嫌いは変わらなかった。学校に行かず、ジャズ喫茶に入り浸った。店にあるアルバムを片っ端からリクエストをして、在学中にそのほとんどを聞き尽くしたという。ジャズに興味を持ち始めたのはこのころからだった。本場の人たちは何を考えて、何を話すのかを知りたくなった。
そこでアメリカ・ボストンのバークリー音楽大学への留学を決意する。サックスを初めて手にしたのは、大学入学と同時だった。「学校がこんなに楽しいものだって思わなかった。先生も先生ズラしないし、先生も生徒も対等なんだよ。その中で、先生と違う意見を生徒が述べても、先生が『僕は違うけど、そういう考え方もできる』って認めたわけ。ちょっとショックだった」
教官は自分の考え方の方向性ははっきりと生徒に示した。だが、生徒が教官と反対の方向性を持っていても踏みにじるわけではない。その反対の方向性で、1番力を発揮できるところに行きなさいとアドバイスする。
当時、まだ完ぺきではないが、自分の目指す方向性がボヤボヤとだったが、田野城には見えていたという。
「それで、それを追求したくなった。自分と同じような方向性を持っていると思える人に会って話がしたかった。自分が好きだと思える音楽を創り出す人たちがどんな生き方をしているか見てみたい、何をしゃべるのか聞きたい」
高校時代にジャズ喫茶で聞いたアーティストの中で1番好きだったのは、サックス奏者のデイブ・リーブマンやだった。そこで田野城は大学在学中に、リーブマンやその師匠のジョー・アラッドらを訪ね出す決意をした。
カネや技術ではない−エモーショナル
幸運にも、最初にデイブ・リーブマンの師匠であるジョー・アラッドのレッスンを受けることができた、田野城はその場に泣き崩れたという。
「音楽はスピリチュアルで、エモーショナルなものだ。技術じゃない、気持ちが先に来るんだ、技術はその次だって。アラッドはそう言った。それを表現する場合に技術があったほうがいいが、絶対に逆になっちゃダメだって。それで僕は本当に感動してしまった」
アラッドが口にした言葉は、田野城自身が漠然と感じていたことだったという。ただ、それまではその思いを確認する相手がいなかっただけだ。自分と同じ思いを、尊敬する一流アーティストがもっと明確な言葉で語り出したことで、田野城は「完ぺきにノックアウトされてしまった」というほど、感動を味わったという。
大学卒業後、日本に帰国し、大阪のライブハウスなどで演奏を繰り返した。しばらくすると、田野城のもとにキティレコードから「レコードを出さないか」という話が舞い込んだ。
「でも、日本の音楽関係者の考えは、アラッドらとは全く違ってたんだ。音楽とはレコードの売り上げ枚数だって。僕が考えているような音楽は売れないから辞めなさいって言われた。こうしたほうが売れるからって」
だが、アラッドらに指導を受けた田野城は、自分の考え方の方向性に自信を持ちはじめていた。そんな田野城と日本の音楽業界の考え方の妥協点として生まれたのが、キティレコードから出された田野城のファーストアルバム『ストーン』だった。
彼の演奏というより、彼の生き方に参った
モントルージャズフェスティバル
「しばらく音楽が聞けない状態になったんだ。サックスも吹けなくなった・・・」ふがいない思いでファーストアルバムを出した後も、田野城は日本の音楽業界とことごとくもめた。
アメリカでは当然のこととして認められることを主張しても、日本では踏みにじられたという。もう音楽は辞めようと2年間、サックスを手にしなかった時期もあった。そんな時、田野城と同時期にデイブ・リーブマンに師事していた、サックス奏者のビル・エバンスが日本にやって来た。
「演奏が始まってから7、8分でその場に泣き崩れた。彼の演奏というより、彼の生き方に参った。同じことを志していたはずなのに、彼のほうが数段、はるかかなたにいっていた。自分が情けなくなった。それでカンバックしようと思った」
田野城が、モントルージャズフェスティバルに出場したのはこのライブから3年後の1991年のことである。ライブハウスなどでのうわさを聞きつけたという広告代理店の電通が田野城に出演オーディションを受けるチャンスを与えてくれた。モントルーは名実ともに世界でナンバーワンを誇るジャズフェスティバルで、91年は25周年のアニバーサリー。プロデューサーはクインシー・ジョーンズだった。
田野城の音楽を聞いた彼は「お前はだれにも似ていない」と言って出演を認めた。出演者はスティング、アニタ・ベイカー、レイ・チャールズ、マイルス・デイビス、エルビス・コステロ、ディ・ライト、ハービー・ハンコック、ジョージ・クリントン、デビット・サンボーンなどそうそうたるメンバー。その中に、ビル・エバンスもいた。
この年、湾岸戦争が起こっていた。テロを恐れて、セッティングが大幅に遅れたことを、田野城は覚えている。
自分の感性に近い街、ニューヨーク

「モントルーという看板を付けたからと言って、それがなんぼのもんじゃいという気持ちはあるよ」と田野城は言う。だが、欧米人と一緒に仕事をしているうちに、日本と欧米で「オリジナリティー」の言葉の意味が違うことに気が付いたという。
「英和辞典には『オリジナリティー』は『個性』と書いてある。僕も『個性を出す』という意味だと思っていた。でも本当は『自主的に自分が思っていることをやる』という意味なのよ。欧米では結果よりもその行動自体が評価される。もっとうちにあるものを出してこいって」
日本人全体が世間体を気にするあまり成熟した個人が確立していないのだとしたら、音楽プロデューサーに方向性があるはずもないし、そこから生み出される作品にうさん臭さを感じる人も少ないのではないか、というのが田野城の結論だった。
「もう自分の意志を曲げてまで日本の音楽業界とは仕事をしたくない」そんな思いから現在、自費でニューヨークのアーチストらとアルバム作りを進めている。
ニューヨークは田野城がいま、もっとも自然になれる街だ。摩天楼。コーヒーショップ。殺伐とした地下鉄。冬の朝にマンホールから上がる煙。ビルの谷間から見える青い空。さまざまな人種、さまざまな文化。孤独。死。そして愛。そういったニューヨークの風景、人々の雰囲気を眺めたときの気持ちが、メロディーとなって自然と沸き上がってくるという。
つまり、ニューヨークが、田野城の人生観、世界観のイメージに1番近い風景を持つ街なのだ。
美しいだけじゃダメ。汚かったり、醜かったり、殺伐としていたり・・・
自分の思いを素直に表現

「美しいだけじゃダメ。汚かったり、醜かったり、殺伐としていたり・・・。だけど、その中に、わずかに、人間の希望が見える場所がいい・・・」
そういった「場所」が田野城にとって1番自然な「場所」であり、そんな「場所」に身を置くと、メロディーが心の中にが生まれてくるという。今はニューヨークが、その「場所」だ。その風景から生まれる音楽は田野城にとっての世界観そのものなのだろう。
「音楽を通して求めていることは、自分の固定観念をそぎたいというか、よりナチュラルになりたい。何が1番自分にとって自然体なのかということを一生かけて追い求めていくと思う」
ステータスや社会的な地位を求めるより、自分がより自然になることを求めるほうが「より生きてるって感じがして、本当に幸せなときがあった」という。「人間魂だね。演奏しているときに、肉体が無くなって、魂と音とが混じり合ったドロっていう感じがほしい。そういう音楽を作りだす環境がほしい」
ニューヨークでレコーディングしていると、田野城はアメリカ人アーティストに感嘆させられることが多い。普段は冗談ばかり言っている彼らだが、美しい夕日を見ると静かに「美しい」と言う。そうした姿勢を眺めている「自分ももっとストレートにならないと。鎧(よろい)を捨てて、自分が思っていることを素直にできるようにならなければ」と思う。
「日本ではそんな風に話す音楽家にあまり会ったことはない。でもね、人間はいつ死ぬかわからないし、いま生きているすべてを投下したいね」
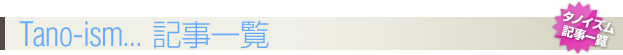
- Facebookページに「いいね!」してください(スタッフ) [最新情報](2025年07月21日)
- 【オレ、ジョーアラッドになってる】 [最新情報Tano-ism音楽教育海外留学その他](2022年07月02日)
- 脳梗塞再発? 技術レベルがゼロになった…公演への意気込み語る🌈…後半には、田野城オススメ体調改善ポイントの紹介も♪ [最新情報Tano-ism音楽教育その他](2022年06月27日)
- すべてはうまく行っている㊗️ [Tano-ism北海道その他](2022年06月18日)
- みなさんご一緒に細胞を活性化しましょう❣️ [最新情報Tano-ism](2022年06月05日)
- お馬鹿な事をした話 ~長文ですが皆さんの参考になれば幸いです~ [Tano-ismオススメ北海道その他](2022年05月31日)
- 気分は超ハッピーに‼️ [Tano-ism北海道その他](2022年05月18日)
- 生かされていることに感謝❣️ [Tano-ismその他](2022年05月09日)
- すべてが新しくなっていく🎶 [最新情報Tano-ismその他](2022年03月02日)
- 誕生日のメッセージありがとうございます! [最新情報Tano-ismその他](2022年02月26日)
僕の言葉では、音楽は、人が人を想う「愛」だということになります。
http://www.tanoshiro.com/m/