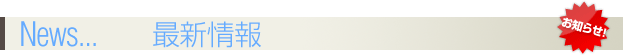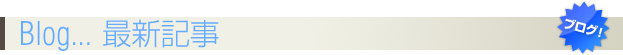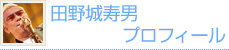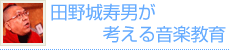日本の音楽業界になじめない私の理由
週刊朝日別冊「現代ニッポンにおける人生相談」1997年6月15日号/朝日新聞社 インタビュアー:和多田進
楽器も英語もできないけれど、アメリカの音楽学校目ざして飛んでいってしまった僕

--- 高校を卒業するまで田野城さんは楽器を扱ったこともなく、楽譜も読めなかったそうですね。
高校を出るまでは大学に行くのか何をするのか、ぜんぜん決めてなくて、とりあえず長く外国に滞在したいと思ってたんです。それで留学を考えました。高校からジャズを聴き始めて、本場の人たちが何を食べて、何を見て、何を考えているのか知りたかった。
後に僕の先生になって下さったデイブ・リーブマンにすごく興味を持っていて、ぜひ会いたいと思いました。住んでいる所は知らなかったけど、アメリカに行けばいるだろうって。
ジョージ・ラッセルというコンポーザーの方やジョー・アラッドというサキソフォンの大先生にも会いたかった。
--- マニアックだったんだ。
そうですね。当時はフォークソング全盛期の時で、ギターの弾き語りが出来る人はクラスの人気者だった。で、ぼくはと言えば教室の片すみでスイング・ジャーナルを読んでいた。変人あつかいされていたんです。でも本場ジャズの音楽家達を知るためには楽器をやらなきゃいけない。それでぼくはサックスを選んだわけです。
--- でも・・・。
縦笛くらいは吹けました。アメリカに行く前には楽器も買った。
--- どうしてサックスだったの。
ジョン・コルトレーンを体に感じたんです。決定的だったのはエルビーン・ジョーンズの『ライブ・アット・ライトハウス』という二枚組のライブのアルバム。サキソフォンプレーヤーがデイブ・リーブマンとスティーブ・グロスマンだった。
それからマイルス・デイビスの後期のアルバムのサキソフォンプレーヤーがやはりデイブ・リーブマンとかスティーブ・グロスマン。聴いて、すごいショックを受けました。
--- リーブマンを聴いただけで選んだわけ?不器用な人間は、あの楽器の姿だけで恐れちゃいますよ。
専門家になる気がなかったからじゃないですかね。ちょっと触ってみた、という程度の話です。
--- 18歳だったわけですね。
卒業は18。でも、ぼくは日本の大学受験に失敗するんです。日本の大学に入りたくなかったから失敗は大賛成ってわけでしたけど。
--- 勉強ができなかったんだ(笑)。
ハイ、そのとおりです。特に受験勉強が嫌だった。

--- 勉強をしないで高校時代は何をやっていたの。非行少年?
一般論だと非行少年だったかもしれない。群れをなすのはダサイ、やるのだったら一人でやると。
--- 登校拒否?
自分では重役出勤と呼んでました(笑)。朝の授業にだけ行って、帰りはそのまま大阪・難波のジャズ喫茶に入りびたって本を読んだり、英語の単語を覚えたりしたんです。
--- アメリカに行こうと思って?
漠然と何かしら求めていたということですね。それが何だかよくわからなかったです。でも、さきほどのエルビーン・ジョーンズを聴いて、よし、アメリカに行ってみようという気になった。それが19歳。資料を取り寄せて調べて、日本でTOEFLを作っている先生に習って、TOEFLは免除してもらった。
--- それで、どの大学に行くかということになるわけですね。
どういう学校かわからないけれども、とにかく行ってみようじゃないかと。それでバークリー・カレッジ・オブ・ミュージック、つまりバークリー音学院に行った。
--- 学歴に関係なく行かれる学校ですか。
基本的には高卒が行く学校ですけど、飛び越し入学もできると思いますよ。教職課程は取れないと思いますけど、演奏家になるなら関係ありませんから。
--- 学校では、音楽理論も教えるけれど演奏家も養成するわけ?
そうなんです。
--- かの有名なNYのジュリアード音学院もそういうことなの?
音楽のカリキュラムやシステム、哲学がぜんぜん違います。NYにはジュリアード音学院とマンハッタン音学院という有名な学校があって、ボストンにはニューイングランド音学院というのがあります。これが東海岸ではもっとも授業内容が充実している。バークリーはどちらかといえば、いかにスピーディーに音楽家として食っていけるかを教える学校じゃなかったかと思うんです。
--- 「格」は同じなのですか。
同じなんですけど、アメリカの学校は普通、単位のトランスファーが認められます。1年目はジュリアード、2年目はマンハッタン、3年目はフィラデルフィアのコンセルバトワール・スクール・ミュージックに行きたいという場合、最後に卒業した学校が卒業証書を発行する。
ところが、バークリーの場合、どこも単位を受け取ってくれません。ニューイングランド音学院に単位を持ってトランスファーしたいと申し出たんですけど、単位を一切合切捨てるのであるのならいいだろうと言われました。バークリー音学院はきわめて専門学校に近いものだとぼくは判断しています。
しかし、もっとも日本の大学と違うところは、落とすための試験はやらないということです。君のウィークポイント、君はここが弱すぎる、ここをもう少し強化してから来たほうが楽だよ、といろんなアドバイスをしてくれます。
わかった、じゃあ、一緒に勉強しようね、ってアメリカの先生が言ってくれて、試験に合格

--- 楽譜が読めなくても入れてくれる音楽学校があった!
あるんです。ふところがメチャメチャ広い。それに、アメリカの大学の先生のすごいところは、まずはみんなフラットに教えてくれます。グレードの違いがあってもチャンスは広げてくれる。みんなに門は広げるけれど、プロとしてやっていけるかどうかは別だという意味の厳しさも教えてくれる。
1年目の寮生活で、日本でしか生活をしたことのないぼくは白人と黒人との3人部屋になったんです。映画で見る以外の外人と生まれてはじめて一緒に生活をしたわけです。四六時中、朝も昼も晩も、寝ているときも起きているときも。これが最初の大きな驚きでした。
ぼくは技術がなかったですから、本当に謙虚な気持ちで勉強することができました。ジョージ・ラッセルはバークリーにはいらっしゃらなかったので、ニューイングランド音学院の教授の方々とかボストン・シンフォニーの方々の力をお借りして会わせてもらったり、特別に彼の自宅でレッスンを受けさせてもらったり、またデイブ・リーブマンの下で勉強ができるようにもなりましたし、ジュリアードのOBの方の力をお借りしてジョー・アラッドにもサキソフォンを習いました。
--- バークリーのときですよね。
そうです。
--- 譜を読めるようになるのにだって時間がかかるでしょう。
すごく時間がかかりました。こらがドで、これがレで、これがミなんだよと教わったんです。先生が「音楽がわからないから音楽大に来たんだろう、何も嫌がることはないよ」と最初におっしゃってくださった。最初のオーディションはアンディ・マギーという黒人の先生で、ランクの振り分けが決められます。
--- 緊張したでしょ。
楽器を持ってノックすると、入ってこいと言うから、名前を言って、ジャパンから来たとか言ったんです。「OK、OK、この譜面を読め」読めるわけないじゃないですか(笑)。なんとか、ボヘーと音が出せるだけで演奏なんてまともにできっこない。
するとマギー先生が「そうか、譜面は読めないんだな、わかった、じゃあブルースをやろう」ってピアノで12小節のジャズのブルースを演奏してみせた。ワンコーラスを終わっても吹けない。
「おまえはなんで吹かないんだ、ブルースが吹けないのか」「ブルースっていうのを知らないんです」。日本の演歌のブルースしか知らなかったんです。『夜霧のブルース』みたいなの(笑)、本当なんです。
ぼくは、これで学校を追い出されてしまうかもしれないと思った。でも先生はニコっと笑って「OKだ」と言うの。「わかった、じゃあこれからいっしょに勉強しようね」って。それからサキソフォンはこうやって吹くんだよ、持ち方はそうじゃない、こうやって持つんだよ、ああやって持つんだよということを教わって、それでだんだんと力がついたかどうかは知りませんけど、一応吹けるようになってしまったんです。

--- そうなるまでにどのぐらい時間がかかったのですか。
4年間ぐらいかかりましたね。楽譜を読むのがすごく遅いほうで。音は比較的バヘーッと鳴っていたけど譜面を読めない、ジャズもできないという、まれな生徒だったみたいで先生も驚いていましたね。
--- それで卒業するときがくる。
ジョー・アラッド、ジョージ・ラッセルの二人に推薦状を書いていただいて、デイブ・リーブマンに習っているという、ものすごい履歴書を持ってニューイングランド音学院を受験しました。
ところがジミー・ジェッフェリーという有名なサキソフォンの先生はジョー・アラッドが大嫌いだったんです。それで、入試のオーディションで、彼が「こいつは駄目だ」と言うんです。
ほかの先生たちは、「いいじゃないか、何が悪いんだ」と言うんですけど、ジミー・ジェフェリーだけが「こいつは駄目だ、こんな吹き方はありえない」って言うんです。相当、推薦状が気に入らなかったみたいです。あとでいろいろ理由がわかるんですが。
--- 試験は初見でやるのですか。
初見で、ワン、トゥー、スリー、ハイですよ。学校のリズムセクションの生徒がいっしょに演奏してくれるわけです。
--- どこか見所があったのかな?ツラ構えがいいとか(笑)。
後から聞いた話では、ジョー・アラッド先生は「学校にとって非常に重要だろう」というすばらしい推薦状を書いて下さったそうです。デイブ・リーブマンが日本に来たときぼくの親と会って、面倒を見るからニューヨークに来るようにと言ってくれたそうです。
ものすごく変わっていると言われたんですって。もしぼくにいいところがあったとしたら、それはイノシシのような突進力だったんじゃないかと思うんです。先生方はチャンスを与えてやろうじゃないかというふうな広い気持ちでいらっしゃたんじゃないですか。
生意気だ、お前なんか追放してやる!と音楽業界のエライ人に、言われてしまいました

---- ニューイングランド音学院はそれでも通ったんですか。
通りました。でも、結果的には行かなくなっちゃうんです。発表の前に日本に帰ってきて。日本に帰った後、ニューイングランドから勉強しようじゃないかという返事をもらったんです。でも1年間だけ日本で演奏してみようと。
--- ようやく譜面が読めて吹けるように、なったばかりなのに生意気だ(笑)。
むちゃくちゃ生意気だと思います。アドリブができない人間が、吹いてみようじゃないかというんですから。自分がどういうものなのか、たぶん試したかったんです。ジャズクラブでは演奏するチャンスを与えていただけなかったので多目的ホールみたいなところばかりで演奏していたんです。そうしてるうちに、キティレコードと3枚契約して、結局28歳まで日本にいることになった。それで1枚製作して、2枚目から問題が起き始め・・・。
--- どういう問題?
音楽とはいったいなんぞや、という問題に関して、大きな隔たりがあることに気づきはじめたんです。その隔たりが最終的には日本の音楽シーンと決別していくことになった。要するにレコードの売り上げ枚数の高いものがいい音楽なんだということなんですよね。
--- キティレコードとの結末はどういうことになったのですか。
当時、小椋佳の弟さんが会社のポジションの高い方でいて、その方に田野城君、レコードの契約が満期なのでこれで決別しようじゃないかと言われたんです。それでぼくは追放してくださいと言って本当にやめた。
こんな生意気なやつは見たことないと言われました。泣きを入れてくるのが普通なのに、何だおまえは、と言うわけ。この業界から追放してやるって(笑)。それで途方に暮れていましたけど、1年間ぐらいはゆっくり考えようじゃないかと、考えたんです。
--- またニューヨークに行った。
そうなんです。結局はアメリカに行きたかった。アメリカで通用しなくても、1からチャンスを与えてくれるあのアメリカに戻ろう、と考えたんです。日本のミュージシャンの方には、グレードの高い方はたくさんいらっしゃいます。ですけど、その水槽というか、環境というか・・・、自分が泳ぐ海が汚いんですよ。東京湾のどろどろとしたヘドロのところで泳ぐより、珊瑚礁に行って気持ちよく泳ぎたかったということです。

--- 29か30歳のときですね。
ええ。そのときにとんでもないことが起きたんです。電通の部長さんからとつぜん電話をいただき、何が何だか分からないまま出かけてみると「きみの話はいろんな方から聞いている、きみは何がしたいんだ」と言われた。
「ぼくはアメリカとか欧米でやりたいんです」
「どういうことなの、具体的に言って」
「ぼくはモントルーに出たい。アメリカのジャズフェスティバルに出たいし、ヨーロッパで演奏活動もやってみたい」と言った。
そうしたら、本当にモントルーに出ることになっちゃった。
--- シンデレラ・ボーイだ。その後、日本の音楽状況についていろんなことを考えたのでしょう。
考えさせられましたね。音楽とは何なのかを教えるはずの音楽大学と教授陣の考え方が閉鎖的すぎます。音楽家を志す人達がもっと自由に、ジャンルを越えて勉強したくてもそれが出来ない。教育システムがまったくつくられていないわけです。
と言う事は、幅の広い人材を生み出せないと言う事です。音楽家にとって作品を発表する事も大変重要な役わりですが、その場合、レコーディングをするエンジニアが本当に重要になってきます。
しかし、日本ではエンジニアの勉強をしたくても学ぶ場所、システムが存在しないのです。
レコード会社のプロデューサーやディレクターも同様で、その言葉の意味も欧米とは違います。日本のレコード会社に素晴らしいプロデューサーとかディレクターがもしいるんでしたら、ぼくは是非お会いしたい。
レコードの売り上げ枚数だけしかわからない彼らにクオリティの高い音楽を売り出そうという発想は育たない。何が芸術かわからないのだから。
ボクはクインシー・ジョーンズがプロデュースした「モントルー・ジャズフェスティバル」に出演して、プロデューサーとは何かを知らされた。現在ジム・ベアープロデュースによる作品をニューヨークで制作中ですがこの過程で、芸術に対する意識の高さをあらためて感じましたね。
--- 教育の問題もありますね。
教育が一番大きな問題です。大学を卒業しても、大学は何らサポートしないじゃないですか。ジュリアードでもニューイングランドでもサポートしますよ。ワークショップというカリキュラムもそのひとつだし、音楽家の力をどのように社会に還元していくのかということを考えて先生は教えます。
日本の音楽学校の場合はお金だけです。すべてマネー、マネー、マネー。お金は重要です。でも、ミュージックビジネスとアートというものの区別ができないですよ、日本はぜんぜん。
フレーズがどうの、バイオリンの音色がどうのといった単純な問題じゃなくして、「おまえらの社会自体が成熟してないじゃないか」というふうに外国から言われている。それがいったいなぜなのか、教育も含めて考えなくちゃどん詰まりになってしまうんじゃないですかね。
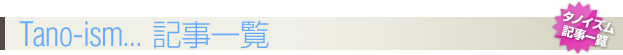
- Facebookページに「いいね!」してください(スタッフ) [最新情報](2025年07月21日)
- 【オレ、ジョーアラッドになってる】 [最新情報Tano-ism音楽教育海外留学その他](2022年07月02日)
- 脳梗塞再発? 技術レベルがゼロになった…公演への意気込み語る🌈…後半には、田野城オススメ体調改善ポイントの紹介も♪ [最新情報Tano-ism音楽教育その他](2022年06月27日)
- すべてはうまく行っている㊗️ [Tano-ism北海道その他](2022年06月18日)
- みなさんご一緒に細胞を活性化しましょう❣️ [最新情報Tano-ism](2022年06月05日)
- お馬鹿な事をした話 ~長文ですが皆さんの参考になれば幸いです~ [Tano-ismオススメ北海道その他](2022年05月31日)
- 気分は超ハッピーに‼️ [Tano-ism北海道その他](2022年05月18日)
- 生かされていることに感謝❣️ [Tano-ismその他](2022年05月09日)
- すべてが新しくなっていく🎶 [最新情報Tano-ismその他](2022年03月02日)
- 誕生日のメッセージありがとうございます! [最新情報Tano-ismその他](2022年02月26日)
僕の言葉では、音楽は、人が人を想う「愛」だということになります。
http://www.tanoshiro.com/m/