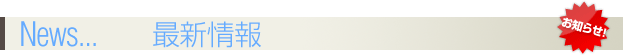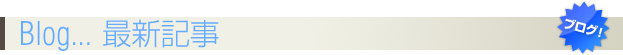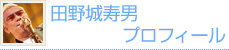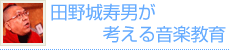ワン&オンリーで突っ走れ!
「PIPERS」(パイパーズ)1993年11月号 構成・文章:T.SATOH
「お前が一番なんだか分からない」と言われ、モントルーのオーディションに合格した。
「リディアン・クロマティック」のテナー奏者、雌伏5年のモノローグ。ワン&オンリ−で突っ走れ!

クインシー・ジョーンズに認められ、91年モントルー・ジャズフェスティバルに日本代表として出演した田野城寿男。ライブも少なく、メディアに露出することも少ない彼には、しかし熱烈なファンがいる。日本ジャズ界の体制からは異端視されがちな、彼の一匹狼的な生き方を、4時間に渡って本誌に告白。
91年7月、モントルー・・・
ジュネーブに着いたのは夜。迎えの車でホテルに向かう途中、雨のレマン湖を走りながら、さすがにモントルーの大舞台への緊張感がジワーッと襲ってきた。「会場を覗く?」という誘いを断ってホテルに入り、ラジオをつけて熱い風呂に入ろうとした。と、モントルーの中継が耳に飛び込んできたんです。
ちょうど僕の大好きなミルトン・ナシメント(ブラジル音楽を世界的に有名にした大御所)が歌っていた。その時、突然ブーイングが出たんです、露骨に。信じられなかった。出来が良くなかったみたい。それ聞いて、風呂の中でブルッと震えちゃいましてね(笑)。僕の出番は1週間後。自分にこう言い聞かせました。とにかく名前じゃないんだ、ベストを尽くすだけだと。
編成ですか?僕一人です。本当は5人編成で行くはずだった。が、いろんな事情から直前に僕一人のセッティングに変更されたんです。バンドはどうする?というのでステージにMacを持ち込む案も出たけど、ヨーロッパでMacは故障が多いというのでボツ。じゃあ、とスタジオに入ってレコードを作った。曲のつなぎを全部決めてワン・ストーリー全部をレコードに入れた。それをDATに落とす。1台だと故障したときに困るから2台持ち込み、本番では予備の1台も作動させておく。
だからステージには一人で上がりました。1対数千人の勝負ですよ。過酷でしょ(笑)。食うか食われるかです。もともと僕はシングルネームでやって来たから、生きるか死ぬかみたいな覚悟はあったつもり。が、モントルーのプレッシャーは想像以上でしたね。プロボクサーの気持ちってあんなんじゃないかな。頼れるものは自分しかない、という。
クインシーがOKを出した
クインシー・ジョーンズがモントルーでなぜ僕を使ったのか。オーディションで彼が言ったことばは、今でも覚えてますよ。彼はこう言いました。「もっとも固まっていない奴だ」こいつの方向性は見えるんだけど、サウンドの志向も演奏もまるで固まっていない、予測ができないって。
普通、日本人が向こうに行くと、例えばピアノはハービー・ハンコックとか、サックスはパーカーとか、歌はマンハッタン・トランスファーみたいだとか言われちゃう。日本ではそれが賛美されて、レコードも出る。でも向こうじゃ、全部NO!です。そんな中で「お前が一番なんだか分からない」と言われ、それで受かっちゃったわけです。
もちろん、「分からない」ままじゃ僕も浮かばれませんからね(笑)。だったら、今度は自分のオリジナリティを徹底的に磨いて、もう一度モントルーに行ってやろう。オーディションで言われたことばを、逆に叩きつけてやろう。そんな気持ちが俄然、湧いてきた。こうなったらリターンマッチだと。だから、ここ2〜3年の僕は、もう一度モントルーに戻るためのセッティング、すべてをこの一点に集約させてやってきたんです。まわりから見るとこの5年間、休んでるように見えたでしょうね。ライブもほとんどやらないしね。だけど、自分ではじっくりと方向性を見極めようということです。
だって、ライブやってもしょうがないじゃないですか。こんな封建的な日本のジャズの風土では。この国では、誰かの真似をすることに対して賛美される。そこから一歩でもはずれると、「そんな演奏ってないじゃない」と言われてしまう。バークレー時代からの友人がブルーノートに出たとき、「君の演奏は素晴らしい。第ニのパーカーみたいだ」ってインタビュアーに言われて苦笑いしてましたけど・・・情けないですね。うわべしか見れないのでは。
日本には渡辺貞夫さんと日野皓正さんという、僕もすごく尊敬するスターがいらっしゃるけど、お二人を代表とするようなこの路線から少しでもはずれてオリジナリティを追求しようとすると、とたんに拒否、または無視されてしまう。「もっとこれっぽくなくちゃダメ」とか、「もっとこれっぽしてくれ」とか、レコード会社の思惑も、「スタンダードを10曲入れてくれ」なんてものばかり。僕にとってこの精神的なギャップはすごく大きい。そんな中で自分を露出させて行くべきなのか、行かない方がいいのか。それをず−っと考えてきました。
いかにその人が本当の力を発揮するかどうかが重要
ソロの回しに興味はない

僕がアメリカで師事した先生ージョージ・ラッセル、デイブ・リーブマン、ジョー・アラッドの3人が3人とも、「オリジナリティを追求しろ」と口酸っぱく言いました。中でもジョージ・ラッセルに傾倒して彼の門下に入り、非常に革新的な理論をいろいろ教わっただけに、僕はどうしてもその世界、ショービジネスじゃないいわゆる「本格派」の世界で自分のオリジナリティを追求していきたい。
よく、僕の音楽は難しいと言われるんですよ。だけど、お聴きになった通り、難しくもなんともないでしょ。つまり、僕の音楽にはレッテルが貼れないから評価が難しい、という意味だと僕は解釈してるんですけどね。
「ジャズ」「フュージョン」「ロック」それぞれのレッテルを信奉する人間には、僕の音楽は敬遠されます。僕のスタンスを理解し、任せられるプロデューサーークインシーは「OK、いいじゃない!」って言ってくれたわけだけど、そんな人も今の日本にはいないような気もする。
「ジャズミュージシャンですか?」と聞かれれば、僕は「はい」と答えます。僕だってパーカーやコルトレーンは大好きだし・・・。だけど、コルトレーンの音楽をこの手で作り直そうという気は、申し訳ないけれどさらさらない。コルトレーンよりはブリティッシュ・ロックーピーター・ガブリエルとかスティングとか、極端なはなし坂本龍一やYMOの方が僕には興味があるんです。
僕はジャズの「インタープレイ」に重きをおく人間じゃありません。ニューヨークの連中のように、それで楽しくやるのは結構だと思うけれど。このあいだの渋谷クアトロのコンサート(8月27日)でも、ソロの回しはほとんどなかったでしょ。ジャズがそのための音楽だとは全然思わない。
形からいえば、僕にとってのジャズは、もう「ワン&オンリ−」で結構なんです、と。いかにその人が本当の力を発揮するかどうかが重要だと思うから。それで思い出したけど、ギル・エバンスのオヶにマイルスが出る、というので見に行ったことがある。さすがにマイルスとなると誰も前に来ませんよ。やっぱり彼しかいない。それ見て僕は、「そうじゃなきゃいけないんだよね」と納得した覚えがあります。
でも、こんなこと言うと、日本ではますます体制派から外れてしまうのね。「反体制派」だと。じゃあ、お前の音楽は何なんだと聞かれれば、僕は「楽曲」だと答えます。すなわち、全体のト−ナリティ感覚だと。
音のパッチワーク!
いま全米ではブラック・サウンドのダンス・ミュージックが荒れ狂ってますが、僕の場合はロンドン系のハウス・ミュージックを取り入れたジャズ、「動」のハウスじゃなく「静」のハウス・ミュージックみたいなところでやっている。
ライブでは相当な音量で鳴らし、かつ気持ちよいセッティングというものを心がけます。ドシーン、ドシーンと来るけれど、気持ちよい。そういう音楽も実はあるんだ、ということです。
ここ10年、音響技術が非常に発達し、エンジニアの腕もすごく良くなっているし、マイクも素晴らしいものが出来ています。ところがジャズやクラシックの人たちは、こういった環境の中で、増幅して遊ぶ、ということにまだほとんど気がついていないのね。最初に気がついたのはロックの人間です。どうすればドラムの音がこうなるか、どうすれば音にもっと距離感が出るかとか、彼らはものすごい意欲でこの面を開拓してきた。
これに対してジャズの人間は、マイクを突っ込んで鳴らすだけ。パーカーの時代と大差ないんです。だから出来上がったレコードのクォリティも両者に開きが出る。
例えば、ニューヨークの「パワーステーション」でレコーディングされたものと、普通のジャズとをCDにかけるでしょ。出て来る音が明らかに違うわけ。この違いは一般の人の方が敏感に感じ取れるんです。彼らは、どっちが気持ちいいか、どっちが快感を得られるかで判断しますから。専門家は、フレーズの構造的な面にしか注意しませんね。
機材を使ってどう増幅するか、それをどうコントロールするか、僕はその辺をめざしているから、ロックの人間は僕の音楽にすぐにヴァイブレーションを起こしてくれます。
ジャズの人間は、「そのフレーズはもっとこうしたらいいんじゃない?」と・・・。僕にしたら、フレーズなんてどうでもいい。もっと全体をどうすれば気持ちよくなるのか。例えばアコースティック・ピアノの残響がどう響けば気持ちいいのか、その辺を考えた方がいいんじゃないですか、と僕は言うんですけどね。この面では、ロンドン勢は素晴らしい音を作りますね。
彼らはファッションから音楽に入っていく。音のパッチワークに目を向ける。ドンと叩いたとき、ポーンと弾いたとき、それをどう処理するかをロンドン勢は考える。
アメリカ系は、もっと全体を意識する。しかし音の効果から言えば、音が前に出るか後ろに出るかでずいぶん違ってくるんですよ。そういったことをコントロール出来るエンジニアも、残念ながら日本にはまだいないと思う。でも、今や音楽するのはプレイヤーだけじゃない。それを増幅させる人間のウェイトもかなり高い、というのが僕の考えです。
その意味で、パット・メセニーなどは70年代後半から優れた機材を駆使して、トータル・ミュージックに非常にウェイトをおいた活動をしていた。いまメセニーのライブに行くと、ほとんどレコードと同じ音がステージにあるんですね。ステージでスタジオと同じような音を鳴らしながら、みなそれに乗っかって演奏するだけなんです。
僕は今までずーと「ダメモト」で来てるんです。
20才で音楽を始めた!

僕は20才から音楽を始めた。高校3年のときにマイルス・デイヴィスを聴いて、一種のショック状態に陥ったのがきっかけ。それまではスポーツ少年で、音楽のオの字も知らなかった。サックスを始めようと思ったのは、その時マイルスのバンドで聴いたコルトレーンやエルヴィン・ジョ−ンズのアルバムで聴いたデイブ・リーブマンの演奏が頭から離れなかったからです。
大学受験に失敗したとき、親は「大学までは面倒みてやろう」と言ってくれました。そのとき、僕は密かに計画を練った。「大学はどこでもいいの?」と聞くと、親は「ああ、どこでもいい」と。それを言質にとって、こっそりバークレーの書類を取り寄せたわけ。英語の先生のところに行ってTOEFLの受け方を聞いたりしてね。
バスーンの浅野高瑛先生に「ソルフェージュを教えて下さい」と飛び込んだのは、その時です。「音楽のキャリアは?」と聞かれて「ない」と答えました。「だったら早いとこアメリカに行きなさい」と先生は言って下さった。たまたま先生は、バークレーに近いニューイングランド音楽院を卒業され、そこで憧れのジョージ・ラッセルが教鞭をとっていた。いま振りかえると不思議な縁を感じます。
バークレーの5年間は非常に辛かった。授業についていくだけで精一杯。日本の音大を出られてバークレーに入ったような方々と違い、こっちはイロハから教えてもらわなきゃいけないわけだから、音楽にまでとても手が回らない。
言い訳するわけじゃありませんが、アドリブ吹き始めたのは、25才からです。もう、ハダカのまんま突っ込んで行ったようなもの。そう、ダメモトですよ(笑)。僕は今までずーっと「ダメモト」で来てるんです。音楽を始めたときに、自分にこう言い聞かせた。「他人と一切比較はしない」「自分の音楽を作ることだけ考える」人は人、俺は俺。
その意味では「プロ」にはなれないだろうと思った。その世界にぶつかって行けば行くほどハジキ飛ばされるだろうって。幸い、いろんな人が手を差し延べてくれて今まで来れたんですけどね。
ジョージ・ラッセルを紹介してもらえたのも浅野先生のおかげだった。先生と一緒にタングルウッド音楽祭に参加し、そこで紹介して頂いたニューイングランド音楽院の先生を通して、彼にコンタクトを取ることが出来たんです。
指定された時間に電話をすると、「個人レッスンはしない。私に学びたいのならニューイングランド音楽院に入学しなさい」といわれ、一瞬たじろいだけれど、「どうしてもお願いしたい」と懇願したら、OKが出た。
ジョージ・ラッセル
理論家としてのラッセルの地位は、アメリカでは非常に高い。ジャズだけでなく、現代音楽の分野にも彼の理論は大きな影響を与えています。ラッセルは40年代にニューヨークに出て、当時の前衛ジャズだったビ・バップを研究し、50年代にそれを発展させた「リディアン・クロマティック・コンセプト」という革新的な理論を編み出した。
マイルスがモード的な手法を多用し、コルトレーンが「コルトレーン・チェンジ」という、それまでのジャズでは考えられなかったような進行形態を考え出したわけだけど、「リディアン・クロマティック・コンセプト」は、常にこうした流れの最先端に位置する先鋭的な理論なんです。
最初のレッスンで彼の部屋に通されたとき、机のうえにはギル・エバンスのスコアが置いてあった。レッスンは理論だけ。楽器は吹かない。ピアノの前に座っていろいろに弾いてみせながら、ワーク・スタディをやっていく。この世界に一歩でも入った人間は、その宇宙的というか無限の可能性を感じさせる理論に興奮してしまいますね。
「リディアン・クロマティック・コンセプト」を言葉で説明するとなると難しいんですが、一言でいうと西洋音楽に東洋音楽的手法を取り入れた体系、とでもいうか・・・ちょっとご説明しましょうか。
結局「イエロー」になるしかないわけですよ。

聴いていると一見メチャクチャ、音がどっちの方向に飛んで行くのか見当もつかない-「リディアン・クロマティック」で吹くとそんな感じに聞こえます。先鋭的なジャズ、ロックの連中たちは、けっこう頻繁にこれを使っている。
例えばロックのスティーリー・ダン。彼らの「Aja」というヒット・アルバムなんか完璧にリディアン・クロマティックで、知らない人が聴くと大抵、気持ち悪がりますね。ハーモニーが浮遊するように動いていくから。が、実はこれは綿密に計算されて作ってある。
リディアン・クロマティックとは?
ドレミファの音階を例にとると、西洋音階ではミとファ、シとドでディミニッシュをつくり、閉じたサークルを形成するわけですが、東洋音階のようにドレミファのファに#がつくとどうなるか?とたんに音の方向性が変わりますよね。トーナリティの中心線がどんどんずれていってスタートラインが曖昧になり、「なんでもアリ」の音の世界に突入していっちゃう。
さらにAug.スケールを考えると、5度を半音上げますから、今までドレミファソとあったものがドレミファ#ソ#となり、今度はそのソ#を軸に発展させていくと、またまた違ったものを取り込んで行ける。これまでのドミソ、レファラ、ミソシのダイアトニックな積み重ねに、ファ#、ソ#を入れることで、今まで使えなかった音が平気でどんどん使えるようになる。親兄弟、親戚、そのまた親戚というようにみーんな引っ張って来れるようになるわけ。
音階の中心線をこうして操作することでサウンドの無限の選択を可能にする、というのが「リディアン・クロマティック」の、まあごく簡単な仕組みです。だから、音がどこに進んで行こうと構わない。ハーモニーの制約から自由になるので、自分の好きなメロディ・ラインを作っていける。「気持ちよければ全てよし」です。そう、要するにメロディ優先の理論なんですよ。
進行は基本的にインターバルで決めていく。9thアップしてm2ndダウンするとか、自分のオリジナル・インターバルをセットし、その中でストーリーを作っていくというやり方。そのインターバル即ち、その人のカラーになるわけです。ハーモニーは重要なようでありながら、実はあまり関係ない。親戚関係を全部ほじくり出せて来るわけですから、一種のパズルにしか過ぎなくなる。
もちろん、一見でたらめに見えて、音の進行は綿密に計算し、キーがどういう風に展開しているのか自分できちんと説明できなければいけない。よく使われるのは「トライアングル」の手法です。12音音階の中をトライアングル上に反復していくやり方。これが実に気持ちいいんですよ。
トライアングルを選ぶと、延々とそれだけで回っていってエンディング感がどこにもなくなる。コルトレーンの「ジャイアント・ステップ」「カウント・ダウン」と言われている手法も、このトライアングルですね。コルトレーンはジョージ・ラッセル(前号参照)のビッグバンドにいたことがある。ラッセルのレッスンで、コルトレーンのその時代のテープを聞かせてもらいましたけど、なるほどと思いました。
ラッセルがリディアン・クロマティック理論を体系化しなかったら、ジャズはいつまでも「守旧派」から抜け出せなかったと思う。「マイルスが発展させた『モード』があるじゃないか」と言われそうだけど、これはあくまでインタープレイの中での話ですね。ラッセルはこれを理論的に、最初から楽譜に書ける理論として体系化したということです。
リディアン・クロマティックで作曲するのがすべてとは、僕はもちろん思っていません。が、例えばウェイン・ショーターのそれっぽい曲を聴いて、「このハーモニーどうなってんの?」と言うのでは、同じミュージシャンとして恥ずかしい、情けないじゃないかと思うわけ。少なくとも分析できる能力は絶対必要だと。
しかし、知識では分かっても体で分かるのは大変。それを使うとなるともっと難しい。そういったトレーニングをラッセルから徹底的に学べたのは、本当に僕にとっては大きな財産です。
「イエロー」しかない!
話がガラリと変わりますが、バークレー時代、僕は寮で暮したんです。3人部屋でルームメイトは白人と黒人だった。毎日彼らと寝起きを共にしているうち、ふとあることに気がついた。
ふだん二人が聴いている音楽が徹底してちがうわけ。黒人は、これでもかというぐらいにブラックしか聴かないし、白人の方は白人ものしか聴こうとしない。無国籍なのは僕だけなのね(笑)。そんな中に混じって生活していて、「イエローの俺は一体何なんだ?」と必然的に考え込んでしまった。
人種のルツボといわれるアメリカの音楽シーンを見ると、文字通り「坩堝」の中で音楽が溶け合い、一つになってしまっているわけじゃない。ミュージシャンたちはそれぞれに自分たちの人種の音楽を追求している。当たり前のようだけど、これが日本では一番理解されていない部分なんじゃないかな。
自分たちのお祖父ちゃんの世代が、奴隷として綿花を摘んだような体験の中から「R&B」が生まれ、黒人が今それを演奏することは、イコール彼ら自身の文化を作っていることなんだ、ということね。そういった本質抜きで日本のプロモーターは、この人いいね、あの人いいね、じゃあ呼ぼうかと、向こうではあり得ないようなグループを組まして引っ張ってくる。
本質うんぬんだけじゃない。リズム体に白人と黒人どちらを使うかで音楽が変わってしまうのに、そういった基本的な配慮すらも日本のプロモーターには欠けている。
バンドを組む場合、その辺の方法論が向こうには自明のこととしてある。結局、なんにも分かっちゃいないわけですよ。そりゃ、お金叩けば彼らは来ます。学生時代の友人たちがツアーで来るでしょ。終いにはどうしてもその話になる。
「結局、なんでもいいんだよな日本は。お金もらえるからいいけど」こう言われて、僕は黙ってるわけにはいきませんよ。裏を返せば、これは自分の問題でもあるんだから。黒人音楽が好きだ、カッコいい、というのでブラック・サウンドにのめり込んでいくのも構わないけれど、海外に打って出た時にそれでは必ず打ちのめされてしまう。だって、僕のお祖父ちゃん「奴隷」じゃなかったんだから。
彼らの中に入って闘っていこうという僕は、だからブラックになっちゃダメだし、白人でもダメ。結局「イエロー」になるしかないわけですよ。「イエロー」としてジャズやって、それで連中から逆にきちんとしたギャラをもらってやろうじゃないかと。
でも「イエローとしての僕のルーツは?」と考えると、もちろん「雅楽」であるわけないしね。広島で育って、川で魚釣ったり山に柿取りにいったり、そんな子供時代の原風景みたいなもの、僕のルーツとしては結局それしかない。そんなものがブレンドされて出てくるんじゃないかな、と思うんですよ。
「あっ、田野城の音だ」と分かってもらえる音を出すこと。
楽器もオリエンタル

その意味ではね、楽器にしても、僕がいま使っているヤナギサワのサックスは日本で生まれ、日本人の職人の手で作られたもの。僕はこれを大事にしたいと思うし、海外のツアーにもこの楽器で切り込んで行きたい。
音楽も楽器もオリエンタル-素晴らしいことじゃないですか!だから、実にいいタイミングでヤナギサワのシルバ−ソニック(ソプラノ、テナー)に出会えたと思います。
特にソプラノがすごくいい。それまで使っていたセルマーの「マーク?」と双璧をなすと思う。性格は「マーク?」とはかなり違って、レコーディングでこの楽器の本領が発揮される、と僕は思う。とてもバランスのいいマイク乗りをするんです。イコライジングかけたり音を増幅したりしても、スマートにいい乗り方をする。「アメセル」だと音が荒れ気味になりますからね。
アメリカでもプレイヤーたちは今、いいソプラノを探しています。「マーク?」があればいいけれど、今はまず「生きた楽器」がほとんどないですから。それで困っている。そこへシルバーソニックが登場して、彼らも非常に注目した。
この前ロスに行ったら、向こうのスタジオの一流どころが「ヤナギサワはいい!」と連発していた。「マーク?」とはたしかに違うけれど、その魅力は充分肩を並べる、と評価していた。ちなみに僕のマウスピースは、最近見つけた「シュガール」というアメリカのハンドメイド。非常にごきげんで、シルバ−ソニックとの相性もいいですね。
一発の音の説得力を
楽器もさることながら、やっぱりオリジナリティのあるサウンドを出す、というのが一番大事なことですよね。向こうの連中の生音のパワーは本当にすごいですから。それに太刀打ちできるパワーがあって、なお「あっ、田野城の音だ」と分かってもらえる音を出すこと。一発の音の説得力、というのかな、それが僕には魅力なんです。
デイヴィッド・サンボーン、ウェイン・ショ−タ−、デイブ・リーブマン - 彼らの音は一発で誰とわかりますからね。師匠のリーブマンのソプラノなんて、ピカ1。あれだけ豊かな表現力で吹かれちゃ、誰も勝てない。だからマイケル・ブレッカーや有名どころは、みんなソプラノを置いてしまったわけ(笑)。
ジュリアードのジョー・アラッドは、音について厳しかった。普通にきれいな音で吹いても。「それでお前は何が言いたいわけ?」と許してくれない。
そんな揉まれ方をしてきたから、僕は音では人に負けたくないんです。技術的には、僕より上手い人はこの日本に沢山いらっしゃる。だけど、音への魂の入り方、フレーズのスピード感、ゴリ押しと言うかな(笑)、そんな点では、そうそう人に負けない自信はあります。悪いけれど、ガイジンにも簡単には負けない。相当腕のある人とやっても、田野城というカラーでは張り合えると僕は思っている。そうじゃないと、とてもこの世界では生きていけません。
先日のライブ(8月27日・渋谷クラブクアトロ)は1年ぶりでした。前にもお話したように、僕の今のライブ活動は全くのアンダーグラウンド。ほとんど告知なしで、言葉は悪いけれど遊びのようにしてやってるんです。
よくニューヨーク・ヴァ−ジョン、ロサンジェルス・ヴァージョンと言いますが、LAのライトなものからNYのヘビーなものまで、ライブでは他人の曲を題材にしていかに自分のオリジナリティを出せるか、というところをやっている。一種の勉強バンドです。
前回のモントルーでは、アルバムなしに出られたのは僕だけだった。だから、今はまずアルバムの製作を優先させたい。そこで初めて、僕のオリジナル・サウンドを露出させるつもりです。そのための曲づくりに、今は時間のほとんどを割いているようなものですね。
同時に、アメリカでのツアーの話も進行中で、NYは「スイート、ベイジル」、ロスは「ベイクド・ポテト」からスタート出来ればと思ってます。幸いバークリ−時代の友人たちが今は中堅クラスに上がってきて、彼らからいいサポートが受けられる。
僕も、バークリ−でアイウエオから教わったわけだから、向こうの連中とやる方がリラックスできるしね。とにかく、今の僕はもう一度「モントルー」に戻るためのセッティングに専念したい。どうやったら世界戦ランキングで闘っていけるのか、というところでこの5年間構想を練って来ました。
そんな僕にとって、これまで僕のステージに喜んで聴きに来て下さった人たちは、本当に感謝しきれない存在ですね。レコードもなく、ライブも少ない人間のコンサートになんか興味も湧かないのが普通。なのに、皆さん興味をもって下さり、楽しんで帰って行かれる。彼らは決して音楽マニアじゃなく、自分の感覚に正直な方たちだと思うんです。そういった人たちにこそ、僕も自分の音楽を聴いてもらいたい。ぜひこれからも応援して下さい。
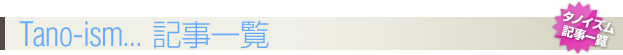
- Facebookページに「いいね!」してください(スタッフ) [最新情報](2025年07月21日)
- 【オレ、ジョーアラッドになってる】 [最新情報Tano-ism音楽教育海外留学その他](2022年07月02日)
- 脳梗塞再発? 技術レベルがゼロになった…公演への意気込み語る🌈…後半には、田野城オススメ体調改善ポイントの紹介も♪ [最新情報Tano-ism音楽教育その他](2022年06月27日)
- すべてはうまく行っている㊗️ [Tano-ism北海道その他](2022年06月18日)
- みなさんご一緒に細胞を活性化しましょう❣️ [最新情報Tano-ism](2022年06月05日)
- お馬鹿な事をした話 ~長文ですが皆さんの参考になれば幸いです~ [Tano-ismオススメ北海道その他](2022年05月31日)
- 気分は超ハッピーに‼️ [Tano-ism北海道その他](2022年05月18日)
- 生かされていることに感謝❣️ [Tano-ismその他](2022年05月09日)
- すべてが新しくなっていく🎶 [最新情報Tano-ismその他](2022年03月02日)
- 誕生日のメッセージありがとうございます! [最新情報Tano-ismその他](2022年02月26日)
僕の言葉では、音楽は、人が人を想う「愛」だということになります。
http://www.tanoshiro.com/m/