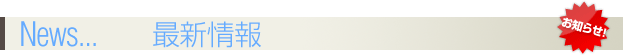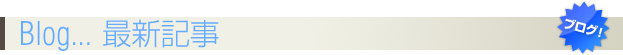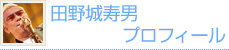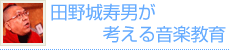リディアン・クロマティック・コンセプトって何だ?
「BRUTUS」(ブルータス)1992年2月1日号/マガジンハウス
君はコルトレーンじゃないんだから、ヒサオのチェンジをつくり出さなければならない。
陽気でパワフルで無国籍な変わり者・・・とでも呼べばいいのだろうか。

テナーサックス奏者・田野城寿男、33歳。なにしろ、ごくありきたりの大学受験浪人1年目のとき、ある日突然といった感じでボストンにあるバークリ−音楽大学留学を決意し、無手勝流で夢を実現してしまった男である。
断わっておくが、音楽的にはまったくのノンキャリアで、である。でも、彼の無手勝流はそれだけに留まらなかった。渡米前に心に決めていた3人の音楽家の懐に飛び込むことに成功し、そのレッスンのなかからミュージシャンとしてのバックボーンをしっかりと身につけてしまったのだ。
そのバックボーンがいかに優秀でコンテンポラリーなものだったかは、昨年の夏、クインシー・ジョーンズに招待されて『モントルー・ジャズ・フェスティバル』に出演したことでもわかるだろう。では一体、彼のバックボーンとはどういったものなのか。そのキーワードが「リィディアン・クロマティック・コンセプト」なのだ。
3人の師との出会い

ぼくが初めてジャズに出会ったのは、18歳のときだった。受験勉強をしながら聴いていたFM放送でジャズに魅了され、見事、大学受験に失敗。ジャズ喫茶に入り浸る毎日になってしまった。
何か得体の知れない強烈なエネルギーに引き込まれた感じだった。なかでもエルヴィン・ジョーンズの『ライヴ・アット・ライトハウス』は強烈だった。このライブに参加していたデイヴ・リーヴマン(テナーサックス)の奏でるメロディーには、頭を金槌で殴られたようなショックと希望を与えられた。
「一体、ジャズとは何なのか?」・・・ぼくはそれを探求するべくジャズの名門 = バークリ−音楽大学に留学し、音楽人生を歩むことになった。ちょうど20歳のときのことだった。
ところで、ぼくには渡米するとき、目的が3つあった。
1つ目は、ぼくに強烈な印象を与えたあのデイヴ・リーヴマンに師事すること。
2つ目は、世界的なサックスのオーソリティーであるジョー・アラッドに師事すること。アラッドは当時、ジュリアード音楽院、マンハッタン音楽院、ニューイングランド音楽院の教授であり、デイヴ・リーヴマンの恩師でもあった。
そして3つ目が、「リディアン・クロマティック・コンセプト」の生みの親であるジョージ・ラッセルに直接、その教えを受けることだった。
ニューオリンズで産声を上げたジャズ・・・。やがて1940年代にチャーリー・パーカーが「ビ・バップ」というスタイルをつくり、ジュリア−ド音楽院を卒業したマイルス・デイヴィスが「モード」を生み出し、ジョン・コルトレーンが「コルトレーン・チェンジ」という、従来のジャズ理論では考えられなかった音楽の進行形態をつくり出し、ジャズシーンを新しく塗り変えてきた。
ジャズは確実に進化し、これまでの感覚だけに頼るものではなく、ヨーロッパで育ったクラシックや民族音楽を取り入れて高度な知識と技術を必要とする音楽になってきたのだ。そしてその最先端を歩んでいるのが「リディアン・クロマティック・コンセプト」なのである。
留学して3年目の夏、ある幸運なきっかけから、ぼくは夢にまで見たジョージ・ラッセルにコンタクトをとることができた。指定された時刻に、ぼくはダイヤルをまわした。
「はじめまして。紹介していただいたヒサオ・タノシロです」
「はじめまして。話は聞いているが、プライベートレッスンできない。生徒をとっていないのだ」
ゆっくりとした、そして明晰な話し方だ。
「ぼくはあなたのつくったコンセプトを学ぶために日本からやって来ました」
「今、どこの学校に通ってるのかね?」
「バークリ−音楽大学です」
「そうか。しかしわたしはニューイングランド音楽院でこのコンセプトを教えているのだから、ニューイングランドに入学しなさい。そうすれば私から直接学ぶことができる」
これにはさすがに参ってしまった。が、このままでは引き下がれない。
「お願いです。一度でいいですから、ぼくにこのコンセプトを学ぶチャンスをください」
と、どうだろう。彼はこう言ったのだ。
「よし、わかった。家に来なさい」
ハーヴァード大学から10分ほど郊外に車を走らせたところに彼の家はあった。チャイムを鳴らす。ドアが開き、そこには背の高い彫りの深い顔立ちのジョージ・ラッセルが立っていた。「よく来たね」と笑顔で差し出された手は大きくて温かかった。部屋に通され、音楽について彼が最初に語ったことはこんな内容だった。
「音楽はインターバル(音と音との距離)だ。太陽を中心に水星・金星・地球・火星・木星・土星と配列されているように、音もまったく同じなんだ。そのなかで自分のオリジナリティーを創り出せ」
次にラッセルは、ジョン・コルトレーンが彼のニューヨーク・オーケストラに参加していたときの演奏テープを聴かせてくれた。
「こうやって自分だけのチェンジ(音楽の進行する形)をつくるんだ。だけど君はコルトレーンじゃないんだから、ヒサオのチェンジをつくり出さなければならない」
この言葉は今でもぼくの音楽理論、音楽観のなかに強く息づいている。さて、それでは「リディアン・クロマティック・コンセプト」とはどういうものなのだろうか。ごく簡略に話してみると・・・。
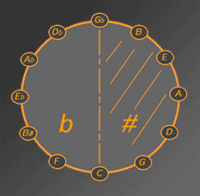
倍音(自然のハーモニックス)というものを突き詰めていくと、12の調性(キー)がちょうど時計の文字盤のように並ぶ(右図参照)。
右半分が#圏、左半分が♭圏になる。さらにこの各調性のなかにそれぞれのスケールとハーモニーがあるのだが、それらの重層的な関係性を明確にし、表現の幅をより豊かにしようとしたものが、「リディアン・クロマティック・コンセプト」なのだ。
場合によっては、“円盤”そのものの軸を動かして、思いもかけなかった調性の関係性、展開を生み出したりもする。バレーボールの時間差攻撃、野球のチェンジアップのような感じ、とでも言えばいいのだろうか。
いずれにしても、現在、アメリカのジャズシーンにおいてこのコンセプトは非常に重要な役割を果たしている。それは音楽を志す者にとってのバイブルと言ってもいい。
幸いぼくはアメリカ留学中、デイヴ・リーヴマンとジョー・アラッドのふたりに師事することもできた。彼らから学んだ多くのことをいつも心に刻み、ぼくはぼく自身の「チェンジ」をめざして頑張りたいと思っている。
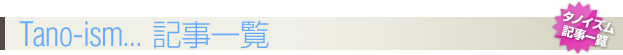
- Facebookページに「いいね!」してください(スタッフ) [最新情報](2025年07月21日)
- 【オレ、ジョーアラッドになってる】 [最新情報Tano-ism音楽教育海外留学その他](2022年07月02日)
- 脳梗塞再発? 技術レベルがゼロになった…公演への意気込み語る🌈…後半には、田野城オススメ体調改善ポイントの紹介も♪ [最新情報Tano-ism音楽教育その他](2022年06月27日)
- すべてはうまく行っている㊗️ [Tano-ism北海道その他](2022年06月18日)
- みなさんご一緒に細胞を活性化しましょう❣️ [最新情報Tano-ism](2022年06月05日)
- お馬鹿な事をした話 ~長文ですが皆さんの参考になれば幸いです~ [Tano-ismオススメ北海道その他](2022年05月31日)
- 気分は超ハッピーに‼️ [Tano-ism北海道その他](2022年05月18日)
- 生かされていることに感謝❣️ [Tano-ismその他](2022年05月09日)
- すべてが新しくなっていく🎶 [最新情報Tano-ismその他](2022年03月02日)
- 誕生日のメッセージありがとうございます! [最新情報Tano-ismその他](2022年02月26日)
僕の言葉では、音楽は、人が人を想う「愛」だということになります。
http://www.tanoshiro.com/m/